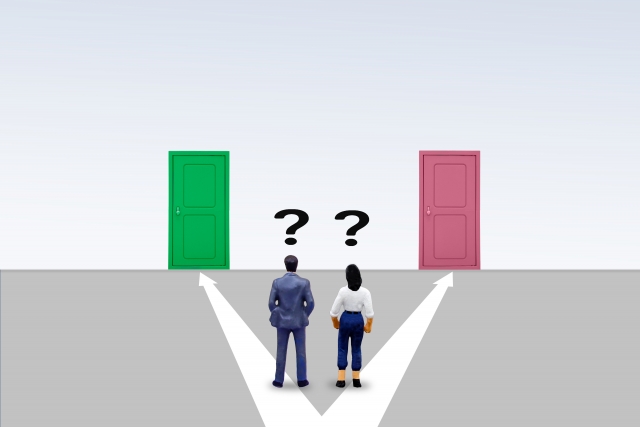中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。
今日のテーマは以下の通りです。
6年生前期スタート~春期講習までの流れと注意点!
6年生は新たなシステムがスタートして忙しくなります。
4年生・5年生の皆さんは知っておくと心の準備ができると思います。
5年後期と6年前期の違い
5年生(後期)と6年生(前期)までの違いを一度整理しておきましょう。
※以下、関東系Mクラスを前提とします。クラスによって多少変わります。
| 5年後期 | 6年前期 | |
|---|---|---|
| 授業日数 | 3日 | 4日 |
| オプション講座 | 国語記述+理科演習 | 前期日特(週1回) |
| 育成テスト | 2週に1回 | 毎週 |
| クラス替え | 2か月に1回 | 毎月 |
育成テストや公開模試の結果がMy NICHINOKENに掲載される順番も、
6年生のほうが早くなります。(受験学年への手厚さ・・・!)
6年前期の注意点
5年で大方の内容には触れるので初出の単元は減りますが、
週の授業数が増え、前期日特が始まり、育テが毎週になるので、
物理的に時間がない、というシーンが増えてきます。
習いごとをがんばって6年まで引っ張ったご家庭も、
ここで整理をする人が多い印象です。(うちもそうでした・・・!)
すでにならった単元を学習するためか、分量が増えます。
特に、社会の本科テキスト、理科の栄冠への道は相当多いです。
国語の読む書くツールなども非常に多いので、
テスト直前にちょろっとやろう!では終わらない可能性も…!
まだまだあくまでも算国優先ではありますが、
理社は5年冬休みの間に少しだけ復習しておくと、
膨大な量であっても耐えられるかもしれません。
算数はN進法やニュートン算など一部の単元をのぞいて、
5年生で一度触れますが、6年では難易度がぐっと高まる印象です。
目指すレベルや学校に応じて、問題の取捨選別が必要です。
例えば、我が家は算数偏差値60前後が多いですが、
栄冠はなるべく全部習得、本科は最後の1,2問は切ります。
加えて「算数強化ツール」という補助問題集が配られますが、
<基礎>はやらず、<共通>は全問、<応用>は数問だけやります。
先生に聞くと、どれをやったらいいか教えてくれると思います。
6年春期講習のポイント
基本的には6年前期の復習です。
校舎によると思いますが、うちは午後に講習授業があるため、
午前に軽く別のワークを入れています。
算数:1行題や、5年「ひとりで向き合うための準備」
国語:語彙ノートを読む
社会:白地図や年表トレーニング
理科:コアプラスの巻頭特集(身の回りの理科)を読む
多いように思われるかもしれませんが、すぐに終わる分量です。
春期講習では触れない単元に触れておくことで、
忘れ去ってしまう単元の再想起を図る、という意味もありますね。
また、授業後には授業でやりきれなかった問題や宿題に取り組みます。
ここでも「分量的に終わり切らない問題」が出てくると思うので、
適当に省きながら進行して、やっていない問題のうちやるべき問題を
先生に質問しながら進めるのが良いと思っています。
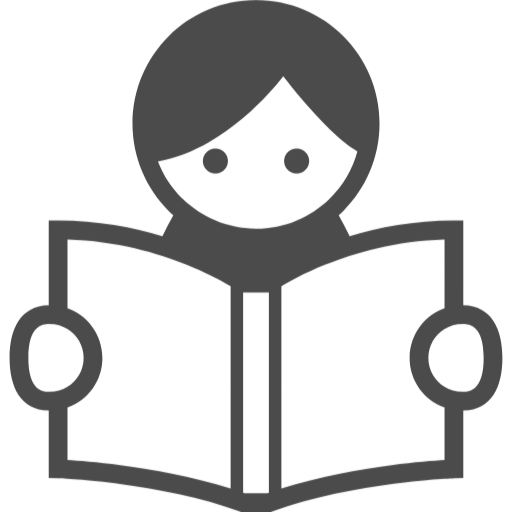
そろそろ受験学年なので焦る気持ちもありますが、
まだまだ子供の感覚では受験本番は遥か先です。
息切れしないように調整が必要だなとは思います。
いかがでしたでし
他の塾ではまた事情が異なるかもしれませんが、
日能研の一例としてご紹介しました。
多忙な6年前期を乗り越えて、夏期講習まで突っ走っていきたいです!