中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。
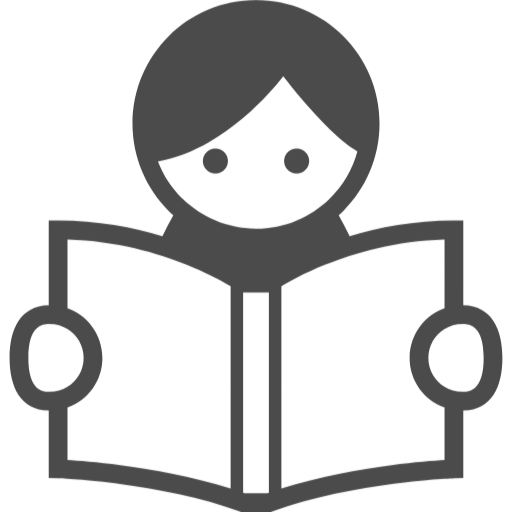
日能研はテストが多い!!
突然失礼いたしました・・・(いつも思っていることがつい・・・)
日能研に通うお子さんをお持ちの方なら、毎週(または隔週)の育成テストに対して
思わずテストが多いなぁと感じることも多いのではないでしょうか。
特に6年生になってからは、育成テストが毎週になるので準備も見直しも大変です。
今回は、限られた時間の中で効率的・効果的に育テ直しを進める方法について、
我が家で実践している方法をご紹介したいと思います。
我が家はプロではありませんが、過去の指導経験と受験生の親としての気づきを、
同じような境遇の皆さんと共有できればと思います。
基本的な姿勢
タイミングを大切に 国語以外の科目は、なるべく当日に済ませることを心がけています。 遅くとも翌日には見直しを完了させるようにしています。(できないこともありますが…) やはり、記憶が新鮮なうちに取り組まなければ「まぁいいか。」になりがちですね。 ただ、国語だけは例外で、要素点が判明してから見直しを行います。 記述問題の採点基準が詳細に分かってからのほうが効率的に直せるからです。 優先順位を明確に 正答率何パーセント以上の問題を見直すか、事前に決めておくことも重要です。 我が家では問題によって柔軟に変えますが一応「20%以上」を目安にしています。 これより低い正答率の問題は飛ばして、基本の定着を優先しています。 4年生は特に注意 特に4年生のうちは、あまり時間をかけすぎないよう注意していました。 見直しは本来、子どもにとって「できればやりたくないこと」だからです。 この時期に見直しを嫌いになられると後々苦労します。 もっと最悪なのは、「見直しがあるから勉強(テスト)が嫌だ」と思われることです。
科目別の見直し方法
科目見直し方法ポイントはおおむね以下の通りです。
算数:解説を読んで理解する(時間がネックだった場合は解き直す)
国語:解説を読み、同じ思考回路で解けるかをイメージ。記述要素の不足を見直す。
理社:時間をかけずスピーディに
各科目の詳細
算数では、まず間違えた問題の解説を子ども自身が読み、理解できるかどうかを確認します。
解説を読んでも理解が難しく、かつ正答率が極端に低そうな問題は、思い切ってパスします。
「最初から何も見ずに解き直す」という方法も効果的ですが、
テスト時間中にある程度時間をかけて出来なかったので、やはり出来ないことが多いでしょう。
時間さえあったら・・・!という問題は何も見ずにもう一度解き直すことが多いです。
国語は点数が出た後に、各問題の解説を丁寧に読み進めます。
選択肢問題は解説と同じ思考回路を辿っていけるかをイメージしながら読みます。
特に記述問題は採点基準が詳しく公表されるため、これを活用しない手はありません。
「どの要素が足りなかったのか」を明確にして、
「その要素は本文のどこから引っ張ってくるべきだったのか」を確認します。
理科・社会は、なるべく時間をかけずに、間違えた問題をさっと見直す程度に留めます。
暗記要素が多いため、間違えた問題を「もう一度覚え直す機会をもらった」と前向きに捉えるよう、
子どもに声をかけています。時々、一緒に詳しく調べることもありますね。
学年別の取り組み方
学年によって見直しの仕方を段階的に変えていくスタンスもおすすめです。
各学年の詳細
4年生では、完璧にやろうとせず、見直しの大切さを伝えながら前向きに、
軽い気持ちで取り組むことを最優先にしていました。
「間違えることは悪いことじゃない。大切なのは、なぜ間違えたかを知ること」という姿勢を、
この時期にしっかりと根付かせることが重要だと考えています。
5年生になると、初登場の難しい単元も多くなるため、わりと丁寧に見直しました。
育成テストが6年前期と違って2週間分の範囲なのであまり大きな穴を作りたくありません。
理解力や処理速度に自信がない子にとっては5年生、特に後期は大変な時期です。
6年生前期は毎週育成テストがあるため、少し効率化を意識するようになります。
あまりに時間をかけすぎると、翌週の育成テスト対策が間に合わなくなってしまうからです。
細かいところよりも、大きな穴を作らないよう意識してメリハリをつけています。
親のサポートはどこまで?
見直しにおいて、親がどこまで手伝うのか、悩むことも多いと思います。
子ども自身にどこまでやらせるのかは、許された時間と相談しながら決めてきました。
我が家では、学年が上がるにつれて徐々に子ども主体に移行していきました。
最初は一緒に解説を読んでいましたが、今では子どもが一人で見直しを行い、
分からないところだけ質問してくる形になっています。
この変化は自然に起こったもので、無理に自立を促したわけではありません。
子どものペースに合わせながら、見守ることも親の重要な役割だと感じています。
まとめ
見直しの仕方は、お子さんのレベル帯や性格、時期、科目によって様々なスタイルがあります。
大切なのは、完璧主義にならないこと。その時にできる範囲でやれば十分だと割り切ることが重要です。
毎週(または隔週)続く育成テストは、確かに親子ともに負担に感じることもありますが、
見直しを通じて着実に力をつけていく子の姿を見ていると、「これは財産だ」と感じることも多いです。
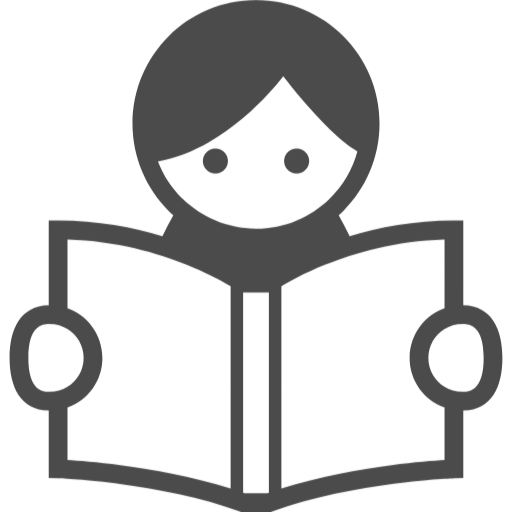
できない問題をできるようにすることが勉強の基本ですからね・・・!
同じような境遇の皆さんと励まし合いながら、子どもたちの成長を支えていければと思います。
何かご質問やご意見がございましたら、お気軽にコメントをお寄せください。



