中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。

公開模試の理科がなかなか取れなくなってきたわぁ
こんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
我が家もそうですが、これにはいくつか理由が考えられるので、
今回はそのあたりの検討を行っていきたいと思います。
日能研全国公開模試の理科 傾向と対策
本日はこちらをテーマにお送りします。
公開模試の理科 特徴とその変化
まず、4年生から5年生、そして6年生にかけて、
我が家の場合は、点数は落ちているが、偏差値は維持あるいは上がっている。
という状態になっています。
みんなにとって難しいというテストになってきているということですね。
テストの内容としてどのような変化があるのでしょうか。
まず、公開理科の問題は次の2種類に大別できると言えるでしょう。
暗記した知識を使えばすぐに解答できる問題です。
4年生では初出単元の知識定着を図ってもらいたいとの意図もあるのか、
やや知識問題の占める割合が高いと思われます。
ただ、6年生の直近公開模試では知識問題の割合が33%でした。
(カウントの仕方によるので、私独自の分析だとお考えください)
暗記ではなく、読み取る、あるいは計算することで解ける問題です。
裏を返すと「暗記した知識を必ずしも使わない」ということです。
理解力や処理能力が鍵となり、地頭の良い子がかなり有利ですが、
問題パターンの経験値や演習量でカバーできるとも考えられます。
直近の公開模試では読解/計算問題の割合が67%でした。
公開模試の理科 求められる能力
5年生の後半あたりから顕著になっていますが、理科は時間との闘いです。
30分で大問5つや6つを処理しなければならないのは至難の業です。
そのため、基本的には読解速度や処理能力の高さが求められます。
- 冒頭の設問文を速く、正確に読む
- 出題意図を瞬時に掴む
- 計算のパターンやルールを理解して問題に適用する
- グラフや表から言えることを理解する(言えないことも意識する)
- 初めて登場する言葉や概念の意味を読み解く
こうした能力は必須になってくると思います。
中学受験段階においては才能や地頭がかなりを占めるとも思われます。
その中学受験においても、演習量でカバーできる部分もあるでしょう。
そして、時間配分などスコアメイクの戦術もある程度効きます。
公開模試の理科 得点のポイント
日々の単元学習をコツコツと進め、演習量を確保することは前提ですが、
公開模試の理科で戦えるようにするためのポイントを洗い出します。
公開模試は入試問題を分析・研究した上で作成されているはずなので、
入試理科にもきっと役立つ考え方になると思います。
- 大問の性質を見抜き、時間のかからない問題を確実に
→基本的には前半に知識問題・後半に読解/計算問題が多い
→前半の知識問題は時間がかからないので即答して時間をセーブ
→後半の読解/計算問題はどの程度時間がかかるかを見積もる
※大問によっては知識問題のみで構成されているものもある - 時間がかかりそうな後半の小問を後回しにする
→(5)まではサクサクいけるが、(6)以降新たな文章が与えられ難しいなど、
小問配点は同じなのに時間がかかる(=タイパの悪い)問題は飛ばす。
→(7)時点で相当複雑な計算が必要なら、(8)はもっと複雑なはずです。
その場合、(8)は一旦飛ばすのが定石であると考えられます。
→ほかの問題が済んだら戻ってきて制限時間まで考えて1問でも解く。 - 本文や設問文で与えられているヒントに敏感になる
→学習量が少なくても点が取れる子の最大の武器はコレです。
出題者の意図やヒントへの嗅覚がすごいのです。
→一見知識問題でも、「なぜここでわざわざ問うのか」を考えます。
例えば、金属と熱に関連したテーマの問題なのに、
実験から分かることとして「壊れやすい」などはほぼダミーでしょう。
(100%そうだとはもちろん言い切れませんが)
理科 6年夏以降の学習
ここまで公開模試の問題特徴を見て頂き、いかがでしたでしょうか。
- 4年生よりも点数が取りにくくなっている。
- 知識問題と読解/計算問題があり、単純な知識問題が減ってくる。
- 時間がないため、取れる問題から取り、タイパの悪い問題を飛ばす。
- 設問文などにちりばめられたヒントに敏感になる嗅覚を養う。
このあたりの理解はとても重要になってくると思います。
夏期講習ではこれまで単元学習で得た知識をもとに多くの演習を行うと思いますが、
- 問題のパターンを意識する(知識、グラフの読み取り、比例の計算・・・)
- 自分が解けるか解けないか、どのくらい時間がかかるかを意識する
- 設問文などから得られるヒント、出題者の意図を常に考える
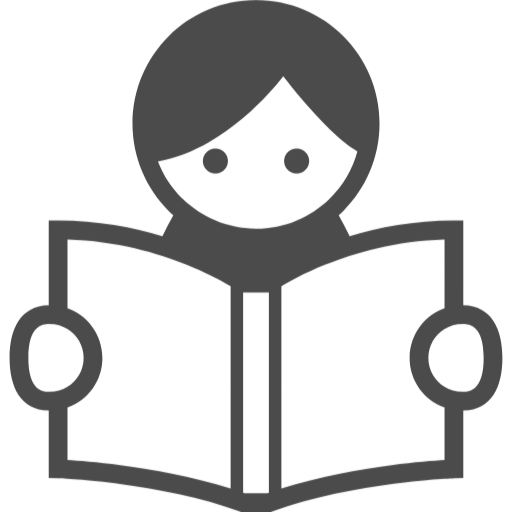
演習時点からどんな時にもこの3点を意識して取り組むことで、同じ模試から鍛えられる得点力が変わってきそうです。
また、特に上位校以上では「なぜそうなるか」が求められてきます。
読解問題でより点数を伸ばすためにも、なぜ?を解説する補助教材は重要ですね。



