中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。
今日はちょっと立ち止まって考える類のテーマを用意しました。
なぜ偏差値が高い学校を目指すのか、ということです。
良い学びの環境を得て、高い学歴を形成するために、
私たちは塾に通い、懸命に戦い、より高い偏差値の学校を目指します。
昨今においてはやや安全志向な学校の選び方が増えてきたので、
「偏差値だけじゃないよね」という見方も広まってきましたが、
それでも到達できるより高い偏差値を目指すという発想は自然です。
それでは、学校の偏差値とは一体何でしょうか。
我々は本当に高い偏差値の学校を目指さなければならないのでしょうか。
この記事が皆さんのお考えを深めるきっかけとなれば幸いです。
目次
偏差値とは何か
ある学校の偏差値とは、「学校の人気度」であり、「学校への入りにくさの尺度」です。
学力の似通った集団が、どの程度の確率で合格できるか?を示す値とも言い換えられます。
「どのくらいの人気で、どのくらい入りやすいのか」ということです。
ご参考)偏差値の統計的な意味
同じテストを受けた集団の中で、個人の位置がどこにあるか、を示した指標です。
個人の点数が平均からどの程度離れているか、と言い換えることもできます。
そのテストの偏差値=(個人の得点 – 平均点) ÷ 標準偏差 × 10 + 50
上記が算出式になります。
個人として点数だけでなく、平均や標準偏差(ばらつき具合)に左右されます。
周りの点数次第で偏差値は上がったり下がったりするわけですね。
偏差値という数値自体は模試ごとにそれぞればらばらな値が算出されるため、
一年間や半年間の偏差値を平均した数値が「持ち偏差値」と呼ばれます。
そして、持ち偏差値別に集団を束ねたときに、合格率が80%を超えるラインが、
「学校の偏差値」(日能研でいえばR4偏差値)になります。
※これらは塾の公表情報であり、実際には様々な調整が行われている可能性もあります。
偏差値のよくある誤解
偏差値については大きく2つの「よくある誤解」があります。
偏差値が高い学校ほど集まる受験生はレベルが高くなります。
そのため、簡単な問題だけでは差が付かず、
結果として難しい問題が含まれやすいというのは事実でしょう。
ただし、偏差値が高いから必ずしも難しいわけではなく、
出題される問題にはそれぞれの学校のカラーがあるはずです。
そのため、偏差値と難しさは連動するとは限りません。
偏差値は人気を表す指標ですが、
その学校の質の高さを直接的に表しているわけではありません。
商品やサービスも、人気が高い=良いものとは言えませんね。
もちろん、質が良いからこそ人気が出るという側面はありますが、
こちらも完全には連動していないでしょう。
質は変わらないのに人気が高騰するケースもあるのです。
これらを踏まえて、学校選びを進めていく必要があります。
偏差値が高くなっている学校は、人気が集まってきている理由が何かあります。
人気が高まれば、定員が増えない限りは倍率が高まるため、
入学試験を突破するという意味では厳しさが増してくるでしょう。
一方、本当は良い教育を施し、良い環境を提供しているのに、
何らかの理由で人気が高くならず、偏差値が上がらない学校もあります。
そうした「本来はもっと価値があるのに・・!」という学校を探すと、
入学試験の労力に対して、得られるものが大きくなるのかもしれません。
偏差値をどのように捉えたらいいか
同じ塾や、同じテストにおいて、偏差値は自分の立ち位置を表現します。
集団の中で、同じ問題を使った時にどの程度できるのか、ということです。
ただし、次の点に気を付ける必要はあるでしょう。
(1) 単発のテストでは結果がブレるから、一回の偏差値で実力は分からない。
→我々はテストの偏差値で一喜一憂してしまいがちですが、結果はブレます。
→本来は数十回の平均偏差値をみたいですが、現実的には半期~通期まとめてになるでしょう。
(2) 偏差値はあくまでも代表値で、結果の全てを表しているわけではない。
→その子の実力(=学力)は、偏差値という1つの単純な数値を見るだけでは分かりません。
・算数で解き筋はどの程度頭に入っているか、手は動くか、図は書けるか・・・
・国語で語彙はどの程度あるか、読む速度は、選択肢は細かく分析しているか・・・
・理科で原理原則を1つずつ理解しているか、身の回りの現象を説明できるか・・・
・社会でグラフを読めるか、理由を説明できるか、時事にアンテナが立っているか・・・
こうした細かい軌跡を見る必要があって、「偏差値」は全てを反映できていません。
ですから、偏差値自体はほんの一部しか今の実力を映していないことを考慮しつつ、
立ち位置の参考情報として数回分を見る。
こういった慎重な見方が本来必要であって、
あくまでも志望校を選ぶときの判断基準の一つにするイメージを持つとよいでしょう。
わかりやすい数値だからこその危うさ(=勘違いしやすさ)がある、ということですね。
偏差値通りの学校にしか入れないのか
これもまた難しい問題です。
半期や通期などの持ち偏差値はたしかに学力のベースを表していると思います。
ただし、それは「模試の問題で言うとその偏差値」という条件が付きます。
私たちの志望校に模試と同じような内容・形式の問題が出るとは限りません。
例えば、オール記述の学校を受けるのに、選択肢問題のテストが参考になるでしょうか。
参考にならないわけではないと思いますが、そのまま偏差値通りの実力が
過去問や試験本番で発揮されるとは限らないということも十分考えられます。
その学校の入試問題と傾向が近い模試・冠模試などはより参考にできるでしょう。
模試の偏差値は、学力のベースを表す数値としては参考にするが、
志望校を受けて良いかの絶対的な基準にはならず、過去問を解いてみて最終判断、
ということが大切な向き合い方だと思います。
そして、対策をきちんとすることで、
持ち偏差値よりも上の学校の合格を得る確率を高めることはできると思います。
偏差値が高い学校を目指さなければならないのか
中学受験に何を求めるか次第だと思います。
何が何でも最終学歴を得るのだ、という場合は偏差値が高い学校が有利に働くことも多いでしょう。
周りのレベルの高さ、授業の進度やレベル感、大学受験に対する知見など、
ハイレベルな進学校だからこそ得られる情報や環境が背中を押してくれる面もあります。
私の通った神奈川御三家の学校も「東大を目指すのが当たり前」の雰囲気があり、
よし!やってやるぞ!と一念発起をする必要がありませんでした。学年上位は当然受けるのです。
そういう環境であれば、もちろんチャンスは増えますし、早めから対策を意識しますね。
その一方で、周りが優秀であるからこそ中高の成績次第では自信をなくしやすい人もいます。
周りの中で自分が「できるポジション」にいたほうが実力を発揮しやすい人もいるでしょう。
このあたりは性格や頑張り次第でもあるので、「優秀な学校のほうが必ず有利」とも言い切れません。
参考) 似た学力の子が優秀な高校に通っても大学受験の結果は変わらない研究
独立行政法人経済産業研究所 成田 悠輔氏コラム
https://www.rieti.go.jp/jp/papers/contribution/yasashii28/02.html
有名校の生徒はその学校のおかげで成績優秀なのではなく、
そもそも成績優秀な生徒が有名校に入っているだけ、という結論だそうです。
※日本ではなくアメリカ・シカゴを舞台とした研究です。
もちろん、中学受験の目的は学歴だけではありません。
同じようなレベルの友達と刺激し合いたい、部活や体育祭を頑張りたい、制服が素敵だ・・・・・・
こうした動機の場合、少しでも高い偏差値を、という考えはフィットしない可能性があります。
私は「努力で到達できそうな高い偏差値を目指すこと」自体には意味を感じます。
受験勉強は自分と向き合い、必死に努力し、必ずしもコントロールできない結果を受け入れるという
非常に有意義な学力・精神の教育プログラムであると思うからです。
※少し過酷になりすぎている/カリキュラムがさすがに過多であると思う一面もあります。
そのような観点で中学受験を捉えたとき、
あまりにも多くの時間を授業や課題に投じるのに「楽すぎるハードル」では効果が限定的です。
届きそうで届かないラインを目指すからこそ、尊い成長のプロセスになると信じています。
これは、勉強だけではなく、スポーツや芸術でも同じだと思います。
多くの時間と労力を割き、この期間はこれを頑張る!と親子で決めた貴重なアクションだからこそ、
相応の負荷をかけて努力をしたほうがいいのではないか。
それには、自分で目指せる高い偏差値を目標とした勉強が適しているのでは、と思うわけです。
受験生本人にとってはもっとシンプルな話かもしれません。
偏差値が高い学校や、そこに入れる生徒のことをかっこいいと思って、憧れる
ごく自然なことですし、そういうことでいいんじゃないかと思います。
後から自分の受験期を振り返った時に、頑張ったなぁと自分を認められることが大切です。
高い偏差値の学校を目指すというのはそれにつながる努力の軌跡となりえます。
まとめ: 偏差値との程よい距離感を
偏差値というのは統計上の数値であり、シンプルですが捉え方が難しい面もあります。
この数値に親が振り回され、子に偏差値だけを追い求めさせることは効果的ではありません。
あくまでも、子どもの学力が身に付いたか、その形跡がみられるかを追いたいものです。
追い方が分からなければ、塾の先生に問題と向き合い、解く力が付いているか確認するとよいでしょう。
※そのことについて回答できない先生はプロではないと私は感じます。
その一方で、中学受験を成長のプロセスと考えたときに、
より高い偏差値を目指して自分に過度になりすぎない負荷をかけることは有意義だと思います。
もちろん「らくな中学受験」を目指してほかの活動と両立することも考え方としてアリですが、
多くの時間を割くのであれば真剣に、本気でぶつかったほうが得られるものは大きいでしょう。
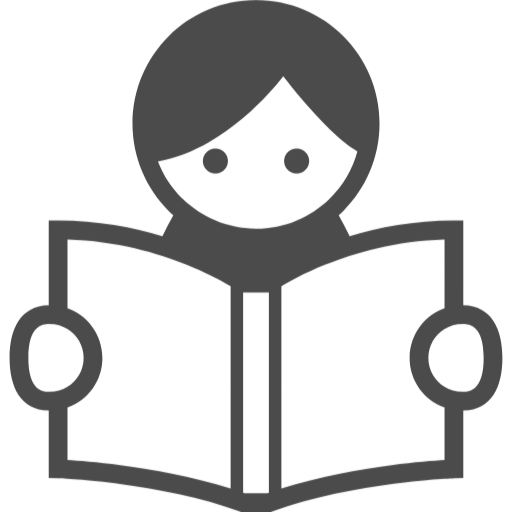
偏差値とどう向き合うかについて考えると、中学受験をどうしたいか、なぜやるのか、というコンセプトに突き当たります。その点を親がしっかりと考え、親子で合意することを私はとても大切にしています。
偏差値については、また考察していきたいと思います。
私は、どの偏差値帯にいる子も、目指す子も、頑張る子たちを応援し続けます・・・!



