中学受験ブログ『中学受験どっくす』のマナトです。
中学受験生を持つ親御さんの中で、「子どもが問題を解けなくて困っている時、どうサポートすればいいのか」と悩まれている方は多いのではないでしょうか。特に5年生、6年生と学年が上がるにつれて問題が難しくなり、親御さんでも解き方が分からなくなってくることがあります。
私自身、過去に少し指導経験があり、今は中学受験生の親として日々奮闘する中で、「分からない問題にどう向き合うか」について考えることが多くなりました。今回は、そんな経験から得た気づきを共有したいと思います。
目次
分からない問題への向き合い方
子どもが問題を解けないとき、どのような選択肢があるのでしょうか。
1. 解答解説を粘り強く読み、自力で解決する
メリット:
- 思考力や問題解決能力が身につく
- 自分で考え抜くことで理解が深まる
- 自己解決の経験が自信につながる
デメリット:
- 時間がかかる
- 解説を読んでも理解できない問題がある
- 誤った理解のまま進んでしまうリスクがある
子どもによっては、粘り強く解説と向き合える子もいれば、すぐに投げ出してしまう子もいますよね。
うちはわりと投げ出しタイプでしたが、「まずは自分で読んでみてー」とお願いし続けてきて、
だんだんと「一回読んでみるねー」という反応が増えました。
本人の性格や得意不得意も考慮しながら、「自力解決」の比率を調整するといいでしょう。
2. 塾の先生に質問する
メリット:
- 質問力が身につく
- 塾の指導方針に沿った解き方を教えてもらえる
- 適切な解説を受けることで効率よく学習できる
デメリット:
- 質問者が並んでいると時間がかかる
- 質問の仕方によっては十分な答えが得られないことも
- 「すぐに人に聞く」習慣がついてしまう可能性
質問することはその勇気も含めて、素晴らしいスキルだと思います。
「まず自分で考える」姿勢を持ってから質問するようアドバイスしたいところです。
「どこが分からないのか」を明確にして質問できれば、より効果的な解説を得られます。
3. 親と一緒に解説を読み、親が教える
メリット:
- すぐに質問でき、解決が早い
- 子どもの理解度に合わせてじっくり説明できる
- 親子のコミュニケーションになる
デメリット:
- 感情のぶつかり合いが生じやすい
- 塾の教え方と親の教え方にずれが生じることがある
- 親自身が理解できない問題も増えてくる
我が家でも、親子で勉強すると時々険悪な雰囲気になることがあります。
これがかなり厄介ですよね。「前も言ったじゃん・・・」と何度思ったことか・・・
そんな時は一旦距離を置き、冷静になってから再開するか、別の解決法を模索します。
また、「よそのお子様を預かっている」と思い込むようにしています。笑
4. 個別指導や家庭教師などに頼る
メリット:
- 塾の方針や子どもの特徴に合った教え方をしてもらえる
- マンツーマンで質問しやすい環境
- 理解度や進度に合わせた指導が受けられる
デメリット:
- 費用がかかる
- 先生との相性がある
- 依存しすぎると自己解決能力が育ちにくい
集団塾では解消できない疑問や、弱点克服のためには効果的な手段となることがあります。
先日、オンライン家庭教師の体験を受けましたが、その時の体験を少し書いてみたいと思います。
体験談:オンライン家庭教師
以前、記事にも書いた「家庭教師のピース」さんで無料体験をしてみました。
↓↓↓こちらのサービスです

結論としては めちゃくちゃ良かった と思いました。
スタッフさんや先生が本当に優しくて、子どもの自己肯定感を守りながら教えてくれます。
お願いした内容としては、公開模試の見直し(算数)です。
当日の問題と解答を事前に送付し、その場で画面共有しながら解説頂けました。
60分の無料体験授業を受けて、現在は検討中です。
もし今すぐに受けないとしても、後期の志望校別対策でお願いする可能性は高そうです。
私もある程度は教えられるのですが、忙しくなったり、子の成長もあったりして、
ずっと私が見るのもな・・・、とは思っていたところで体験できて本当に良かったです。
ご興味のある方はぜひ体験だけでも申し込んでみてください!
基本問題と発展問題のバランス
分からない問題の解決で、意識したいのは基本問題と発展問題の扱い方です。
基本問題は分からないまま放置せず、確実に解決して先に進むことが大切ですね。
単なる「解き方のパターン暗記」ではなく、
「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるレベルまで理解できると理想的です。
一方、発展的な難しい問題については、お子さんの学力や志望校のレベルにもよりますが、
あえて「勇気を持って目をつぶる」という選択も時には必要です。
限られた時間の中で、基本問題の習得を完璧にするほうに時間を使った方が、
結果的に得点力アップにつながることが多いと感じています。
※ただし、これは目指すレベルや受験校の「思考力問題比率」などにもよると思うので、
塾の先生と何をどこまでやるか相談してみてください!
分からない問題と向き合うプロセス自体が成長
「分からない問題を解決するプロセス」自体、子どもの成長につながっていると思います。
問題が解けなくて悔しい思いをしたり、諦めずに粘り強く取り組んだり、
助けを求める勇気を持ったりすることは、すべて将来につながる貴重な経験です。
時には「この問題が解けなくても、こうして解決しようとしている姿勢がまずすごい」と、
プロセスを認めてあげることも重要だと思っていて、結構うちでは意識しています。
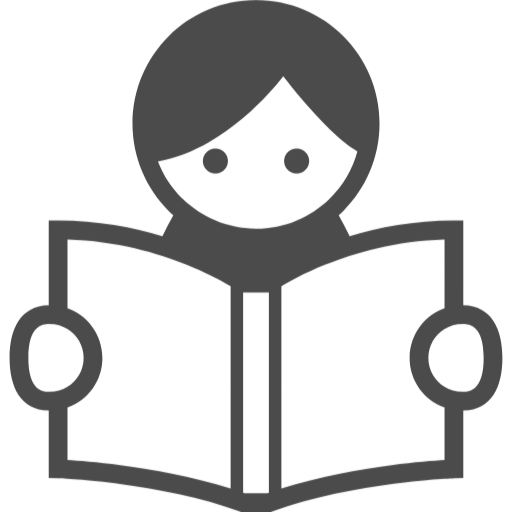
入塾当初の右も左も分からない感じからすると、
解説を読んだり、先生に質問したりするだけで感動です・・・
まとめ
「分からない問題をどうやって解決するか」という問いに、一つの正解はありません。
子どもの性格や学習スタイル、親子関係などを考慮しながら、様々な方法を組み合わせていきたいですね。
基本問題は確実に理解し、発展問題は志望校のレベルに応じて取り組む。
そして何より、「分からない」を放置せず、何らかの形で解決する習慣をつけていくことが、
中学受験を乗り切る大きな力になると思っています。
皆さんの家庭でも、お子さんに合った「分からない問題の解決法」が見つかりますように。



